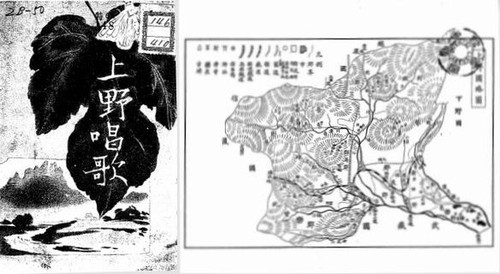方丈記切読12:いとしきもの
2010/3/13
方丈記切読12
「およそ物の心を知れりしよりこのかた、四十あまりの春秋をおくれる間に、世のふしぎを見ることやゝたびたびになりぬ。いにし安元三年四月廿八日かとよ、風烈しく吹きてしづかならざりし夜、戌の時ばかり、都のたつみより火出で來りていぬゐに至る。はてには朱雀門、大極殿、大學寮、民部の省まで移りて、ひとよがほどに、塵灰となりにき。火本は樋口富の小路とかや、病人を宿せるかりやより出で來けるとなむ。吹きまよふ風にとかく移り行くほどに、扇をひろげたるが如くすゑひろになりぬ。遠き家は煙にむせび、近きあたりはひたすらほのほを地に吹きつけたり。空には灰を吹きたてたれば、火の光に映じてあまねくくれなゐなる中に、風に堪へず吹き切られたるほのほ、飛ぶが如くにして一二町を越えつゝ移り行く。その中の人うつゝ(しイ)心ならむや。あるひは煙にむせびてたふれ伏し、或は炎にまぐれてたちまちに死しぬ。或は又わづかに身一つからくして遁れたれども、資財を取り出づるに及ばず。七珍萬寳、さながら灰燼となりにき。そのつひえいくそばくぞ。このたび公卿の家十六燒けたり。ましてその外は數を知らず。すべて都のうち、三分が二(一イ)に及べりとぞ。男女死ぬるもの數千人、馬牛のたぐひ邊際を知らず。人のいとなみみなおろかなる中に、さしも危き京中の家を作るとて寶をつひやし心をなやますことは、すぐれてあぢきなくぞ侍るべき。』」
年を経て色々な事変に遭遇する。しかし、それを記録に残す人は極少ない。更に記録されて
も、長期間保存される事は更に少ない。長明さんの方丈記の記録は貴重であり、歴史資料と
して利用されることもあるようだ。ともかく、大都会の大火災はその損害の及ぶ範囲は際限
がない。それは、承知のうえ都市生活が成り立っている。物が燃える条件を理科の授業で習
った。小さな紙片が燃えるのも都市が燃えるのも原理は同じである。燃えにくい生木も条件
により簡単に燃えてしまう。火が燃え広がる状況では、一種の正帰還状態になっている。燃
えた火で、水分は蒸発して、ある部分が強烈に燃えていれば、周囲も発火温度になり、火が
飛び付くき、可燃物は燃え出す。これが、更なる火力を発揮する。一度、延焼を始めるとそれ
を止める事は難しくなる。合理的に考えれば、火事の心配が多い一等地に家を建てるのは
納得できないだろう。「いにし安元三年四月廿八日かとよ、」は長明さんの実体験であったの
か。ともかく40才代までの体験という事で世の不条理を意識したのであろう。「病人を宿せる
かりやより出で來けるとなむ。」と出火元も書いているのはさすが。ところで、「病人を宿せる
かりや」とは何か。疫病か何かで病人を隔離していた仮小屋なのか。一種の野戦病院を連
想してしまう。宿すとはそこで、衣食住をするので、炊事で火も使ったろう。複数の何人かの
関係者が利用する仮小屋ならば火もとの管理が不徹底になり火災の原因としては納得でき
る。当時、都市の中にこういう施設があったというのも都市機能の点で興味をそそる。
 |
| |x
|x
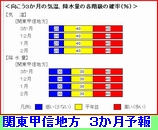
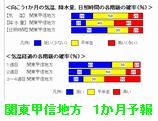

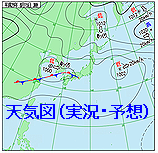
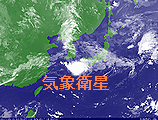
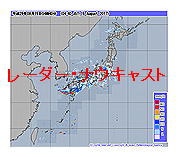
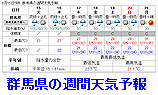
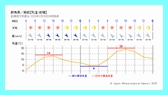





























































































 | 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);