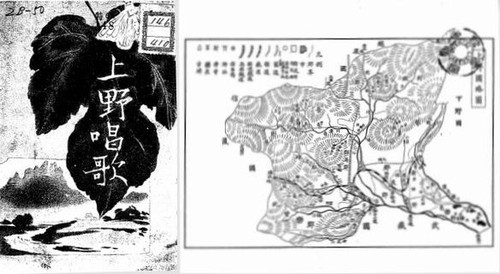読みかじりの記:(高山)彦九郎 歌と生涯(4)
2010/12/16
読みかじりの記:(高山)彦九郎 歌と生涯(4)
○「喪屋で歌作りに没頭」の章
ここには、七首の歌が挙げられている。そのうちの三首を引用する。
■くちはつる身はあだし野の露なるを はかなきものとたれも知らずや
■いろ鳥の声も哀れに墓原を かなたこなたとなき渡りける
■打ちつれて渡る雁がね雨雲を つばさにかけて声かすかなり
著者は「彦九郎は十九歳の時生母繁を失い、二十二歳の時に父正教が死去している。その後は祖母りんが一家の中心になっていたが、天明六年八月二十四日に、気丈で賢明であったりんも八十八歳の長寿を全うして亡くなった。この祖母の死に悲嘆のあまり彦九郎は三年の喪に服することになる。」と述べる。「彦九郎という人は衝動的な行為が多く奇行の人とも考えられているが、この喪屋での生活も異常であった。」と喪屋での生活と彦九郎の精神世界の関係に言及している。三年間も長期の喪に服するだけでも異常とみえるかもしれない。彦九郎は歌人としても優れた才能に恵まれていたとの事で、彦九郎の歌の世界を覗くと、その精神は世俗の些事や評価を超えた所を飛翔していたように見える。高山彦九郎記念館資料によると、墓前日記が 天明7年(1787 )41 歳の時に書かれている。47歳で自刃しているので、祖母の三年間の服喪期間は彦九郎の後半の人生のありかたを決めた充電期間のように感じる。そういう眼で歌を読み直すと、俗人には見えたり、聞こえたりしない自然や社会の摂理に耳を傾け、この服喪期間に重大な決心をしたように感じられる。祖母の孝養というプラスと売名というマイナスの両方の評価があったようだ。三年間の服喪を幕府が佳賞する段階で売名行為と誣告され、実兄専蔵との不和が深まり、江戸に登ったがそのまま江戸に留まり新しい活動を始めた。儒教では父母が死んだとき「三年の喪」に服するという。祖母の死に対して「三年の喪」に服したという事は高山彦九郎にとって特別な意味があったと理解して良いと思う。やはり、高山彦九郎においては生母以上の精神的な位置を祖母が占めていたのかもしれない。
追記1:「三年の喪」は儒教の儀礼とされているようだ。調べてみると、「シリーズ儒教・性愛・志怪1~4(http://www.geocities.jp/jukyosikai/kazoku2/tyosen.html)」における「孝における死と再生」において、「 儒教礼典に依拠する親のための喪は、「足掛け」三年で、実質二十七か月(時代によって二十五か月)である。、まるまる三年ではないとしてもそう短いとはいえない。ところが三年の喪は子の孝心の表現である。孝心やみがたく、三年という規定の喪の期日があけても喪服を脱ぐことをせずにさらに服喪を続けるといった者が時折あったらしいのである。特に三年の喪が自覚的な孝の実践形式としての慣習的定着の途上にあった後漢時代、とりわけその末期にその傾向があったらしい。この時期、さまざまな「過礼」現象、すなわち定められた基準を超過して礼を実践する傾向があったことが知られている。定めの期日を越えた喪服実践のほかにも、親の死に遭ったのが幼少時で孝の自覚をもった服喪ができなかったために、成人後あらためて喪に服す、というようなことも行なわれたという。曹操の敵対者として有名な河北の軍閥袁紹はこれを実践している。それらはおおむね皆手厚い孝心の表明として社会で称賛されたのである。ともあれ規定の三年を越えた服喪という点では、趙宣はその最も極端な例であった。」と述べられている。彦九郎の場合、儒教礼典の親に対する以上の扱いを祖母に対して行っているので、確かに世間からは目立ってしまうだろう。それも、儒教の本家ではなく、日本のつい最近の事である。しかし、祖母にたいする孝心は父や祖父に対する孝心にも通じたと思える。いわば、「三年の喪」に服したという事は、原理主義者として、原理・原則に立ち返って反省、行動する事も時と場合によっては必要だと示しているようでもある。それほど、現実が哀れな姿になっていたのだろうから。
追記2:「高山彦九郎の実像」の「高山彦九郎年表」を見ると、宝暦11(1761)に「伊勢崎の松本晩翠の塾に通う。」とある。高山彦九郎と伊勢崎の接点は更に調査が必要だ。
 |
| |x
|x
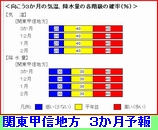
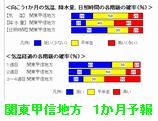

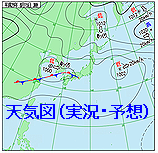
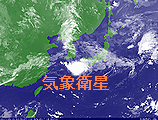
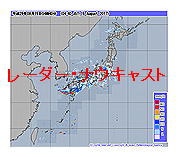
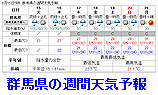
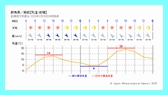





























































































 | 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);