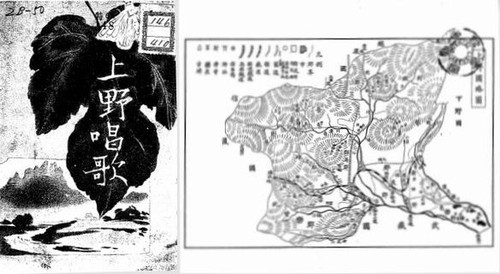有線放送電話の終焉
2008/11/29
有線放送電話の終焉
一般の電話が普及する以前に有線放送電話が導入されていた。有線放送電話の開通以前
は電話は商店とか地域の中核となる家にしかなかった。従って、緊急連絡は電報や「呼び」
電話といって電話のかかってきた家から連絡をとりたい家へ呼び出しをして貰うのが一般的
であった。有線放送電話は放送と電話を兼用したシステムであり、電話の普及の先駆けであ
った。WIKIPEDIAによると、
「有線放送電話(ゆうせんほうそうでんわ)は、農業協同組合(総合JA、専門JA)・漁業協同組合・市町村などの地域団体によって設置される、日本の地域内の固定電話兼放送設備。一般には「有線放送」「有線電話」「有線」と略される。」、
「1960~1970年代(昭和30~40年代)にかけて、日本電信電話公社の一般加入電話が普及していない農林漁村で、市町村地域内の放送業務・地域内の音声通話等を行い、生活改善をする目的で設置されていた。形態は言わば、アナログ音声専門の地域LAN。」
と述べられている。放送内容はプログラムに従った定時放送と緊急・臨時放送があったよう
だ。定時放送は今日のコミュニティ放送局と同じような地域や加入者密着の番組を流してい
た。時には音楽も流れた。電話は放送時間以外の時間帯にする。NTTの回線に接続できた
のか定かではない。有線放送電話が利用されたのが、いわゆる「神武景気」が到来した昭和
30年代であり、同31年には、「電化ブーム」が起こり、『経済白書』に、「最早戦後ではない。」
と謳われた時代であった。経済が豊になると公社の電話が急速に普及してくる。そうして、大
多数の家庭に電話が普及する頃になると有線放送電話はお荷物となってしまう。有線放送
電話がいつ終焉したか定かでないが、個々の家庭レベルでは電話が入った時点で有線放送
電話の役割は終わっていたのであろう。今では、有線放送電話はほとんど忘れ去られて、電
線を張った数本のコンクリート柱が残っているだけである。コンクリート柱の由来さえ分からな
くなりかけている。
 |
| |x
|x
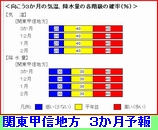
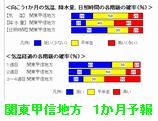
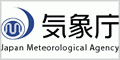
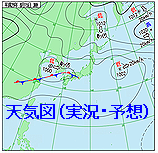
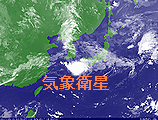
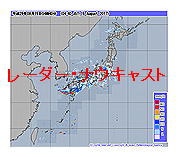
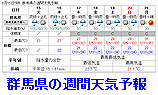
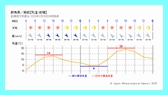























































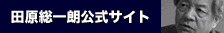


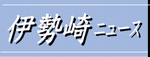
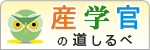













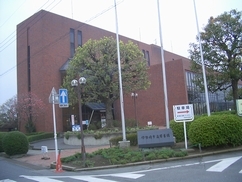

















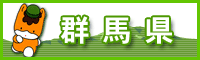
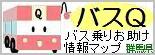
 | 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);