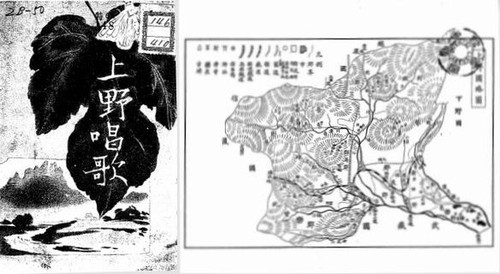寄生虫
2009/7/8
寄生虫
かっては、寄生虫にかかる例が多く、学校で検便をした記憶がある。便を採取して学校へ持
って行く。寄生虫の卵を検出して寄生虫の有無を調べて対策したようだ。自分も腹痛を起こし
たことがあり寄生虫が原因であった可能性がある。虫下しの薬を飲んだ記憶もある。ともか
く、人糞も肥料として使われていた時代が自分の幼年時代にあったのだ。自分のおなかにサ
ナダムシを飼っている学者の本を読んで仰天した事があった。しかし、そのサナダムシも現
在では人体に戻るまでの生活サイクルが断たれてしまって絶滅の危機に瀕しているようだ。
ノミ、シラミに関しては頭髪にDDTをかけられたという話を聞いたことがあるが、自分にはそ
の記憶がない。ノミ、シラミにとりつかれた経験はある。ともかく、自分以外の生物から色々な
攻撃を受けて、人体の方もそれに対応せざるを得ないので何らかの抗体等の防御システム
が働きやすかったのは事実かもしれない。終戦直後の学校生徒の写真等を見るとメタボ症
状の顔はほとんど見当たらない。それよりもやせ気味に見える。食料や栄養分の不足ととも
に摂取した栄養分を寄生虫と分け合っていたのであろうか。寄生虫は究極のダイエット手段
かもしれない。ともかく寄生虫が人体に棲息するようになったのは人類の歴史に匹敵する長
い時間がかかっていると思う。寄生は実は共生だったのか。気になるところだ。
 |
| |x
|x
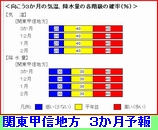
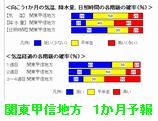
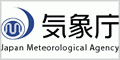
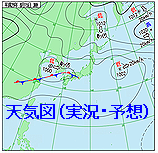
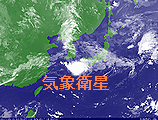
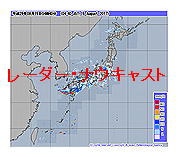
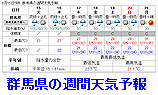
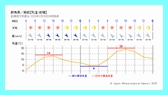























































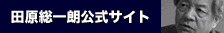


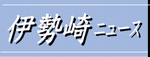
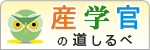













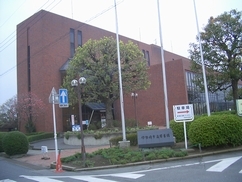

















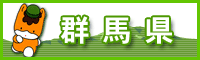
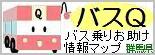
 | 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);