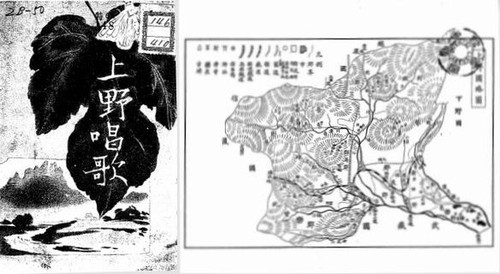2008/10/25
生物の多様性
少年時代は水辺の遊びが多かった。魚捕りや釣りが中心であったが、いろいろな水辺の生
物を見ていたようだ。今日、生物の多様性保護が叫ばれているが約半世紀の間に姿を消し
た生物が何種類あるのか気になるところである。数年前つれづれなるままに、ノートに書き出
したことがあったので、それを以下に記す。正式学名でなく方言名のものもあると思う。
追記(2025/08/05):本日以後に水辺生物以外も追加した種名を()に記入。分類は記録優先で不正確。目撃伝聞も含む。カオジロガビチョウ等外来種は普通に目撃している。ハクビシン、アナグマ等の被害も多発している。最近は生物の多様性が貧弱化して、外来種の進出も目立つ。
(1)魚類等・・・・・コイ、フナ、タナゴ、ハヤ、ガレンバヤ、ナマズ、ウナギ、ドジョウ、スナメンド
ジョウ、ギュギュウ、クチボソ、バッカチ、七つ目ウナギ?、メダカ。
(2)甲殻類・・・・・カワエビ、ザリガニ、サワガニ、ケガニ。
(3)貝類・・・・・バカ貝、シジミ、カワニナ、タニシ。
(4)両生類・・・・・イモリ、アカガエル、トノサマガエル、食用(ウシ)ガエル、ヒキガエル。(アマガエル、ヤモリ)
(5)昆虫類等・・・・・ホタル、ゲンゴロー、タガメ、ミズスマシ、マンガ、羽黒トンボ、ヒル、馬ヒ
ル、ヤゴ。(シオカラトンボ、アカトンボ、キアゲハ、アオスジアゲハ、クロアゲハ、モンシロチョウ、モンキチョウ、シジミチョウ?)
(6)鳥類・・・・・カワセミ、シラサギ、ショウビン、カイツブリ、カモ。(サンコウチョウ、カッコウ、ツバメ、スズメ、モズ、キジバト、キジ、カラス、オナガ、ウグイス、ヒヨドリ、カオジロガビチョウ、)
(7)植物・・・・・ヒシ、オモダカ、コホネ、ネコヤナギ、セリ。(アメリカセンダングサ、アメリカフウロ?、セイタカアワダチソウ、タンポポ:外来種)
(8)ほ乳類(追加):イタチ、モグラ、シカ、ハクビシン、アナグマ。(市内情報:タヌキ、キツネ、イノシシ)
なお、カメもいたような気もするが定かでない。沼で水泳をするとき、ヒシの実を採って食べた
こともある。バカ貝は沼底に足を着けて探し、潜ってとった。焼いてしょう油をたらしてたべ
た。食用(ウシ)ガエルは食用に導入された外来種で異様な鳴き声をする。夜になると水辺で
異様な鳴き声がするので、何かいるのではないかと地域で問題となり、消防車で水をかい出
してみたら、ウシガエルがいたという話を古老に聞いた事がある。残念だが、昔の田、小川、
沼等の水辺は極当たり前の風景で、そこに何が棲んでいるかとうは詳しい観察はしていなか
った。大人や学校も断片的に教えてくれただけであったと思う。結局遊びのなかで係わった
生物だけを記憶していたにすぎないだろう。生物の多様性も多くを失った結果気付いた問題
なのかもしれない。生物に関心が無ければ、名前を覚えようとも調べようともしないだろう。
最近、水利の掘りさらいでタナゴ、フナ、ドジョウ、ナマズ、シジミなどがまだ棲息している事が
確認できた。体系的な調査が必要であろう。
*************************
追記1(2015/1/14):「生物の多様性」の記事がランキング7位に入った。古い記事だが、誰か読んでくれたらしい。場所は男井戸川上流の水田地帯である。「蛍が飛び交った頃(http://af06.kazelog.jp/itoshikimono/2008/09/22/)。(2008年9月22日 (月))」に当時の記憶を書いた。水棲生物が激減した原因に農薬使用(パラチオン等有機リン系の殺虫剤を多用していた)があったが、土地改良で用水を直線の三面コンクリートに変えたことにより、水流に緩急がなくなり、ほぼ急流のみになってしまって、水棲生物が居着く場所が無くなったのも原因と思われる。なお、聞いた話ではカメもいたとの事だ。「マコモ(http://af06.kazelog.jp/itoshikimono/2009/10/post-3ef1.html)。(2009年10月19日 (月))」
キーワード「男井戸川」でGoogleサイト内検索(https://www.google.co.jp/webhp?tab=ww#q=%E7%94%B7%E4%BA%95%E6%88%B8%E5%B7%9D%E3%80%80site:http:%2F%2Faf06.kazelog.jp%2F)。
追記2(2015/2/14):「生物の多様性(2008年10月25日 (土))。」の記事がランキング6位に入っている。1/中頃からランキング入りをしたようだ。
Googleでキーワード「生物の多様性 」を検索(https://www.google.co.jp/webhp?tab=ww#q=%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7&start=340)。(一部だけ表示)
検索結果のトップに、約 813,000 件 (0.27 秒) と表示。そのページを確認したが、約 349 件中 35 ページ目 (0.34 秒) が表示最終ページであり、リストの中に本記事は見つからなかった。
この記事の読者はどこからこの記事へ飛んできたか。ご苦労様と言いたい。Google検索で上位に並ぶ「生物の多様性 」情報発信のurlは「生物の多様性 」を破壊してきた?巨大な組織が多いようだ。一般国民も、自分の目で直接に「生物の多様性 」を確認することは困難な時代になった。Googleで検索しても、WIKIPEDIAでしらべても所詮バーチャルのレベルだ。
「ハトよ 鳴いておくれ:男井戸川と「二枚橋の地名と鬼亀の足跡の伝説」の説明板除幕式(http://af06.kazelog.jp/itoshikimono/2014/11/post-c2d8.html)。(2014年11月25日 (火))」の記事も本記事と関係するだろう
「老人の寝言:寝言を言い始めたのはいつ頃からか;先ず逃げて メダカの大将 また群れる。(http://af06.kazelog.jp/itoshikimono/2015/02/2015-a08f.html)。(2015年2月11日 (水))」。に放流したサケの稚魚がどこまで遡上したか聞いた事を書いた。放流地点の目と鼻の先まで遡上しているが、障害物がそれ以上の遡上を阻止しているらしい。魚道の設置を陳情し、設置される見込みになってきたようだ。まさに、土建国家日本の姿が透けて見える。最近は、大規模工事をする前に環境調査を行うのであろうが、それが形式まで堕落していないだろうか。言い換えれば、いくら環境調査を行っても、悪い開発は悪いのだ。
あそこへ行けば、「生物の多様性 」が見えるというのも、悪い事ではないと思うが、それだけで「生物の多様性 」が保てる保証もないだろう。「生物の多様性 」も「環境」もその破壊者の上っ面を綺麗に見せるだけで終わっているのが多いように感じる。
もっとも、我々農家の先代達は、手ぬぐいを口に巻いただけで、半袖シャツ一枚、裸足で田圃に乗り込んで、あの有機燐農薬のパラチオンを散布したのだが。
追記の追記:Googleでキーワード「生物の多様性 」を検索した場合、検索式の「start=340」があると一部しか表示されない。
Googleでキーワード「生物の多様性 」を検索(https://www.google.co.jp/webhp?tab=ww#q=%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7)。(全項目表示)
*************************
BLOG TOPの 「アクセスランキング」へ飛ぶ
ページ先頭へ飛ぶ
 |
| |x
|x
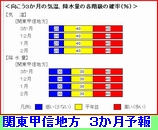
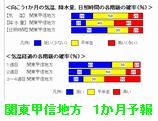
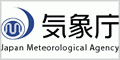
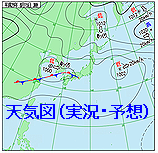
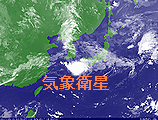
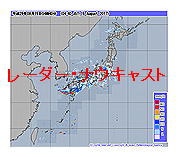
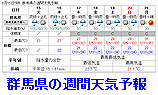
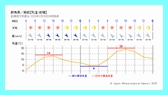























































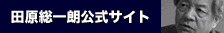


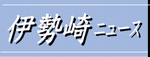
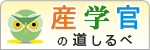













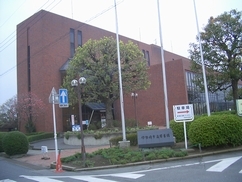

















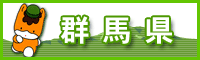
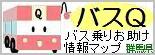
 | 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);