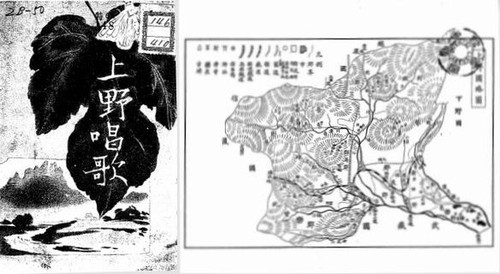2009/9/29
折伏教典
大学の頃だったろうか、かつての友人が我が家を訪れた。どうも宗教がらみであったようだ。
折伏教典という本を示されたと記憶している。大学に入り、受験勉強から解放されて、ふと来
し方行く末を思うとなにがしかの不安を覚える。大学のキャンパスは学問だけではなく、会社
や宗教等の関係者が暗躍する場所でもあったようだ。当然、前衛的な学生団体も活動してい
た。こちらは、ビラとスピーカーの大音声で一般学生を折伏しようとした。自分は宗教活動に
も学生運動にも共感は出来たが積極的に係わる気持ちがしなかった。親父が汗水流して稼
いでくれた金と奨学金だけでこの四年間の学生時代を送らねばならないと考えると当時のノ
ンポリが自然の選択であった。今自分がやるべき事があるのである。自分の理想としては大
学とは講義や実験も普通の人間に無料で開放される事である。皆さん自由に入って下さい。
暴力と喧噪はお断りです。大学は健全な知的バトルの場です。自由に論争・研究・学問をし
て下さい云々。しかし、現実の大学は象牙に塔にもなれず、算盤の上に乗っているような危う
い存在だ。今日も学園紛争時代と同様に大学が活力と目的を失いかけているようにも思わ
れる。青年層の人口が減る。大卒のレッテルもかつて程の効能が薄れた。学ぶ事への疑
問。それなら信じてしまえ。しかし、学ぶことの第一歩は疑うことから始まる。信じる事に迷う
事はあった。キリスト教では無教会派の矢内原忠雄、南原繁に興味を抱いた事もあった。し
かし、宗教と信仰は別物であろう。まだ結論が出ていない。施設、組織、規律という外的な見
える要因が宗教にはつきまとうがそういうものは誰にでも見えるが、誰にも見えないか、極少
ない人にしか見えないものもある。そう言う、どうでもよさそうな事も一人の人間にとっては無
上のものかもしれない。そのような人の心を思うこともなく、これが最高の真理だと押し売りさ
れるのはうんざりである。当時、その団体の選挙運動が自転車とメガホンであったのを思い
出した。それと同じ様な運動を昨今の大政党がやっている。小さいことは良いことだ。原点に
返ることはもっと良いことなのかもしれない。
 |
| |x
|x
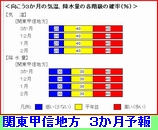
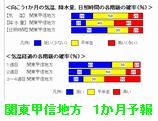
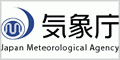
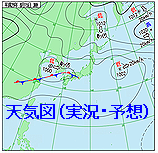
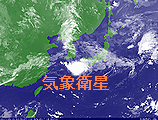
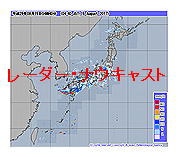
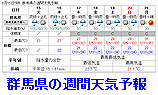
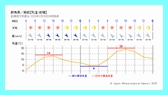























































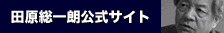


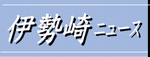
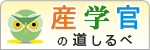













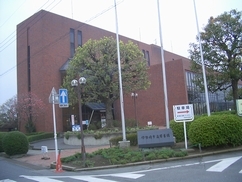

















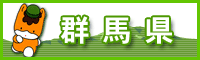
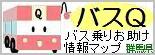
 | 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);