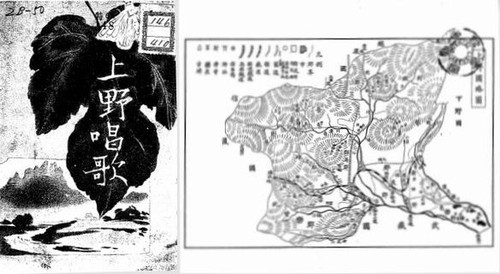2009/7/15
失業対策事業
終戦直後から高度成長期までの間はまだ失業者が多かったようだ。地方自治体が失業した
労働者を雇用したのが失業対策事業であったようだ。道路工事等の公共事業に従事したよ
うだ。自分も当時は通学に自転車を使っていたが、幹線道路もまだ舗装がされていない状況
であった。そこに、大型のバスやトラックと一緒に自転車や歩行者も通っていた。雨の日等は
悲惨であった。でこぼこ道に雨水がたまり、車が容赦なくその水をはねて走り去る。さしてい
るこうもり傘で身を守るのが精一杯であった。こんな道路をつるはしやシャベルでならす仕事
をしていた。高度成長期になるとこのような仕事も余りみかけなくなった。道路工事も機械力
が導入され、そこで働く人も単純な労働から専門性の必要な労働に変わったようだ。今日も
雇用情勢は厳しい。かっては、地方自治体が直接失業者を雇用していたのだろうか。今日は
どうなっているのか。エジプトのピラミッドは失業対策であったという説を聞いたことがある。
一方最近拾い読みした松本清張の『遊古疑考』 で、古墳の謎を清張流に解釈しており、何と
なく納得した。巨大な古墳をある程度の短期間で作るには相当な人員即ち食料が必要にな
る。その食料を余所から持ってくるのではなく、現地調達する為先ず食料生産基地を作る。
結局、一つの古墳を作る事により新田開発が行われ、その成果は継続的に使用できる。従
って、古墳を作る事により生活の基盤・地域開発を同時に行っていた。即ち生活のインフラ
整備が間接的に行われていた。失業対策というより古代の総合的国家プロジェクトと言った
方が正しいのか。逆に今日では失業対策の総合的国家プロジェクトが必要なのではないか。
 |
| |x
|x
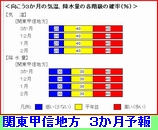
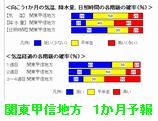
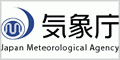
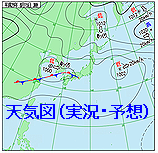
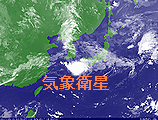
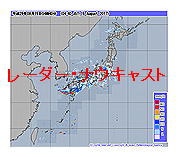
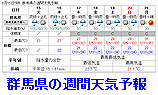
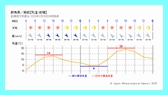























































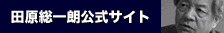


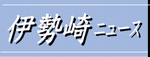
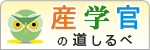













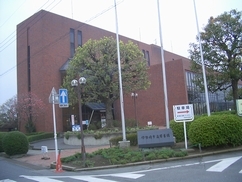

















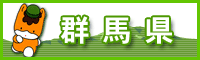
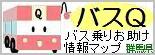
 | 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);