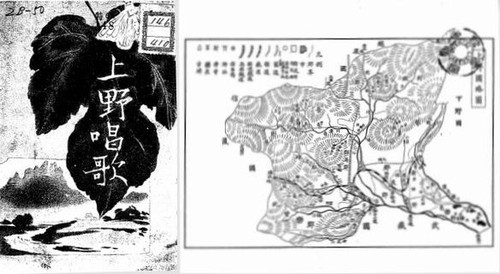読みかじりの記:(高山)彦九郎 歌と生涯(13)
2010/12/29
読みかじりの記:(高山)彦九郎 歌と生涯(13)
○「消えた”九州日記”」の章
著者は「彦九郎は自刃の前日に、手許にあった日記、書類の類を尽く破棄している。」、「同志に犠牲者が出るのを怖れたのである。」と述べてから、彦九郎自刃の様子を記す。
■ことし八つと聞くにぞいとど覚ほゆる 我が子も同じ年と見るにも
■我を思ふ人は有りともあらずとも 恋しかりける故郷のそら
■酌みかはす今日の別れの盃の めぐるがごとにまたも相見む
著者は「彦九郎は妻子のことをほとんど省みない如くだが、熊本を出た菖蒲池村ではわが子と同年配の子を見て心揺らいでいる。子については普段口を噤んでいるだけにその心中が思われる。」と「筑紫日記」の中の歌を記す。「最後の歌は鹿児島県の加治木で心許した同志赤崎貞幹と別れを惜しむところである。彦九郎として天下回天の思想を説いて経めぐる旅であったろうが、歌だけはその心情に幾ばくかの距離を置いている。それが歌の道であったろうが、彦九郎の衝迫した心を救っていたとも言えるだろう。」と締めくくる。ここで著者で歌人である須永義夫の歌に対する考え方の一端が現れているように思える。短歌文学の歌の講評で歌は心情の告白とか述べていたのを思い出す。しかし、心情が歌になるまでには、脳内では色々な作業が行われる訳で、心情そのものではない作品として形を得る。やはり、歌に詠うと時には客観的な分析等も行われる。そう言う点で、歌を作るという行為が感情や心情と理性をバランスさせる働きがあるのかもしれない。
 |
| |x
|x
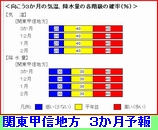
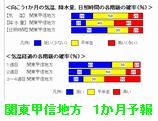

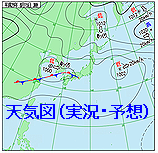
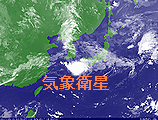
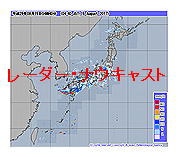
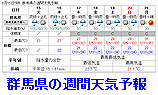
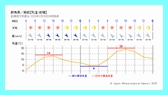





























































































 | 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);
| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);